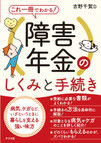障害年金はどんな場合に支給される?

障害年金は、現役世代(20歳から64歳)のための年金制度です。
納付要件を満たして、障害等級に該当していれば、誰でも障害年金を受給できます。
障害年金という存在を知らなかった、自分や家族が該当するかどうかわからないという方は、まずはご相談ください。
障害年金って何だろう?

障害年金は、現役世代が病気やケガで長期間働けなくなった場合に支給される年金です。
障害年金受給の要件は3つ!
よしの社労士事務所では、まず納付要件の確認を年金事務所で行ってから契約致します。年金保険料の納付要件が満たさないと請求そのものが困難になるからです。
1

障害年金の初診日において、被保険者であること。
- 会社員の場合は社会保険加入の期間が厚生年金保険の被保険者です。
- 国民年金の場合は20歳~60歳までが被保険者です。
- 国民年金は、国内居住の60歳~64歳は被保険者でなくても該当します。
- 初診日に20歳前だった方も、障害基礎年金を請求できます。
2

初診日の前日までに保険料を納めていること(または免除申請していること)=未納期間がないかどうかということ
- 20歳から初診日の月の前々月までの全期間の3分の2以上、未納期間がないこと
- または、初診日の月の前々月までの直近1年間に未納がなければ、納付要件を満たします。
- 20歳前に初診日がある場合は納付要件は問われません。
3

障害年金の初診日から1年6カ月後の障害認定日and/or請求日(現在)に、障害等級に該当していること。
- 障害年金は、病気やケガにより、日常生活上の支障や就労の支障が長く続いている場合に支給されるため、1年6ヶ月経過した時点の障害の状態で障害等級を診査します。
- 障害の等級は、「障害認定基準」に定められています。
- 1年6ヶ月後の障害認定日に障害等級に該当しなければ、事後重症請求になります。
障害認定日請求(=遡及請求)とは?
初診日から1年6ヶ月後が「障害認定日」、障害認定日に等級認定されたなら、最長5年分遡及して障害年金を受給することができます。
【障害認定日請求(遡及)できるかどうか?3つのポイントをチェック】
- 障害認定日後3カ月以内に通院していたかどうか?
- 障害認定日頃のカルテが残っているかどうか?
- 障害認定日頃の障害の程度が認定基準に該当するかどうか?
上記3つ、すべてに該当したなら、遡及して受給できる可能性があります!
もし、障害認定日では障害等級に該当していなかったとしても、現在の症状(請求日)において障害等級に該当してれば、事後重症請求を行うことができます。あきらめないで!
障害年金に該当するのは、どんな病気やけが?
日常生活や就労に制限があるなら、原則として、どんな病気やけがでも障害年金の対象になりますが、一部対象外の傷病もあります。
【精神神疾患の例】
- 気分障害(うつ病、そううつ病)
- 統合失調症、統合失調感情障害、妄想性障害
- 器質性精神障害、高次脳機能障害
- 若年性認知症
- てんかん
- 知的障害
- ASD、ADHDなどの発達障害
※パニック障害、不安障害、パーソナリティ障害などの神経症病は原則として、認定の対象になりません。
【内科的疾患の例】
- 慢性腎不全による人工透析
- 糖尿病性腎不全による人工透析
- 慢性心不全、ペースメーカー、人工弁 など
- ガン(悪性新生物)
- 1型糖尿病 、糖尿病合併症
- ME/CFS、線維筋痛症、脳脊髄液減少症、化学物質過敏症 など
【外部障害の例】
- 聴覚障害
- 視力・視野障害
- 脳血管障害による半身麻痺
- 人工関節置換
- 多発性硬化症 など
- 事故や交通事故などによる後遺症 など
障害年金の等級に該当するのは、どんな状態?
日本年金機構の「障害認定基準」により障害等級は決定されます。
「障害認定基準」はこちらをクリックしてください。
障害認定基準の読み方は、慣れていないと難しいですね。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
【1級】
- 身体の機能障害または長期間安静が必要なため、日常生活を送るために、他人の介助が必要な状態。
- たとえば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの。
- 「入院しているなら病室のみが活動範囲、ご自宅にいるなら寝室が主な活動範囲である程度の状態」とされていますが、認定基準に従って等級が決定します。
【2級】
- 身体の機能障害または長期間安静が必要なため、日常生活に著しい制限があり、他人の介助は必要ないが、日常生活は極めて困難で、働いて収入を得ることができない状態。
- たとえば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの。
- 「入院しているなら病棟が活動範囲、ご自宅にいる場合は家屋内が活動範囲である程度の状態」とされていますが、認定基準に従って等級が決定します。
- 人工透析の場合は、フルタイムで就労できていたとしても、認定基準に従って2級が支給されます。
【3級※厚生年金・共済年金のみ】※初診日において会社員・公務員だった方が該当します。
- 労働が著しい制限を受けるか、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
- 治癒していない場合は、労働が制限を受けるか、または、労働に制限を加える必要があるもの(障害手当金程度でも症状固定でなければ3級)。
- 人工関節置換術や人工弁置換術を受け、フルタイム就労できていたとしても、認定基準に従って3級が支給されます。
【障害手当金※厚生年金・共済年金のみ】 ※初診日において会社員・公務員だった方
- 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加える必要があるもの。
- 治癒していない場合は、障害手当金に該当する程度でも、3級該当となります。

社会保険労務士連合会による
個人情報保護認定事務所です。
一般書・専門書のご案内
一般向け書籍
障害年金の手続きをできるところまで自分で進めたい方へ!
社労士向け
不服申し立ての事例集!
社労士向け(共著)
手続きの詳細を解説!
人気ブログ記事
障害年金の情報が満載!
- 慢性疲労症候群の初診日
- 診断書の現症日
- 社労士へ依頼する意味
- 社労士の報酬(倫理)
- グレーゾーンの等級判定
- 認定医は診断書のここを見る!
- 納付要件は第一関門
- 医師の紹介は治療とセット
- 社会保険審査会(第二審)2
- 社会保険審査会(第二審)1
- 初診日を巡る攻防
- 母親の代理受診は初診日になるか
- 雇用保険と障害年金の併給
- 折れない心の秘密
- 年金受給中の新たな病気
- 糖尿病の認定基準改正(2)
- 糖尿病の認定基準改正(1)
- 高次脳機能障害事例(2)
- 高次脳機能障害事例(1)
- 第三者証明とは?(2)
- 第三者証明とは?(1)
- 病歴・就労状況等申立書(4)
- 病歴・就労状況等申立書(3)
- 病歴・就労状況等申立書(2)
- 病歴・就労状況等申立書(1)
- 初診日カルテなし不服申立て
- 発達障害初級指導者講習
- お客様アンケートに励まされ
- 不服申立と処分変更
- 人工関節事例3つ
- 審査請求の落とし穴?
- 言語機能の障害 認定基準改正
- 障害年金請求代理人としての社労士の役割
- 障害年金の提出書類コピーの保存
- 東京地裁判決「障害年金遡及支給命じる」
- 額の改定時期 その4
- 額の改定時期 その3
- 額の改定時期 その2
- 額改定の時期 その1
- 透析の初診日証明
- 就労と障害厚生年金3級受給
- 障害年金の診断書
- 障害年金受給のハードル
- 障害年金 よくある問い合わせ
- 障害年金 年金事務所の対応
- 障害年金と保険料納付
- 医師と社労士の関係
- 患者さんと医師との関係 2
- 患者さんと医師との関係 1
- 良い病院の見分け方
- 障害年金~社労士への報酬
- 障害年金 問題解決手法3
- 障害年金 問題解決手法2
- 障害年金 問題解決手法1
- 障害年金~高次脳機能障害4
- 障害年金~高次脳機能障害3
- 障害年金~専門家への相談
- 障害年金~受診状況等証明書
- 障害年金~高次脳機能障害2
- 障害年金~高次脳機能障害1
- 障害年金~ご依頼~提出まで
- 障害年金~社労士の関与2
- 障害年金~社労士の関与
- 障害年金~障害状態確認届
- 障害年金~医師へ伝える
- 障害年金~受診していること
- 障害年金~脳出血による障害
- 障害年金~介護保険 2
- 障害年金~介護保険 1
- 障害年金~認定基準の変更/眼の障害
- 障害年金~認定基準の変更
- 障害年金~精神疾患の初診日
- 障害年金~社会的治癒2
- 障害年金~社会的治癒
- 障害年金~症状固定
- 障害年金~働くともらえない?
- 障害年金~初診日証明
- 障害年金~更新時
- 障害年金~診断書
- 障害年金~審査請求
- 障害年金~ネットでの情報
- 障害年金~年金事務所
- 障害年金~CFSとFM 認定事例
- 障害年金~治療の地域格差
- 障害年金~健康状態の記録
- 障害者雇用~日本理化学工業
- 障害年金~線維筋痛症
- 障害年金~認知度の低さ
- 障害年金~海外にいた場合
- 障害年金~慢性疲労症候群など 照会様式
- 障害年金~慢性疲労症候群 ME/CFS
- 障害年金~医師の支援
- 障害年金~診断書の日付
- 障害年金~健康診断の結果は保存しておく
- 障害年金 精神疾患と労災
- 障害年金~診断書の信憑性
- 障害年金~認定日という「点」
- 障害年金~点と線
- 障害年金~初回のヒアリング
- 障害年金~医師との交渉
- 障害年金~医師との関係
- 障害年金~本人の申立書
- 障害年金 社会的治癒のつづき
- 障害年金 社会的治癒とは
- 障害年金 初診日が大事な理由
- 障害年金~診断書の訂正
- 障害年金と所得制限
- うつ病~診断書
- 働きながらの障害年金
- 生活習慣病~初診日
- 障害年金と生活習慣病
- 発達障害と就労
- 発達障害の初診日
- 障害年金は所得があったら支給停止なのか?
- 障害年金~傷病の種類
- 障害年金~働いている場合
- 障害年金~初診証明
- 障害年金 決定までの期間
- 障害年金の所得制限
- 障害年金~発達障害の認定基準
- 障害年金~発達障害
- 障害年金~そううつ病の認定基準
- 障害年金~精神疾患の認定基準
- 障害年金に該当する?
- 精神疾患の障害年金
- 障害年金と障害者雇用
- 障害年金~所得制限
- 障害年金~社会的治癒
- 障害年金~障害状態確認届
- 障害年金~初診日と認定日
- 障害年金~海外で受診の場合
- 障害年金とアルコール依存症
- 障害年金~20歳前障害の初診日
- 障害年金の請求 間違いやすいポイント
- 障害年金の請求 社労士へ依頼するメリット
- 障害年金 複数の疾病の場合
- 障害年金の初診日